「漢方薬って長く飲まないと効かないんでしょ?」
「漢方薬って苦そう」
薬剤師をしていると、こんな声をよく聞きますが。
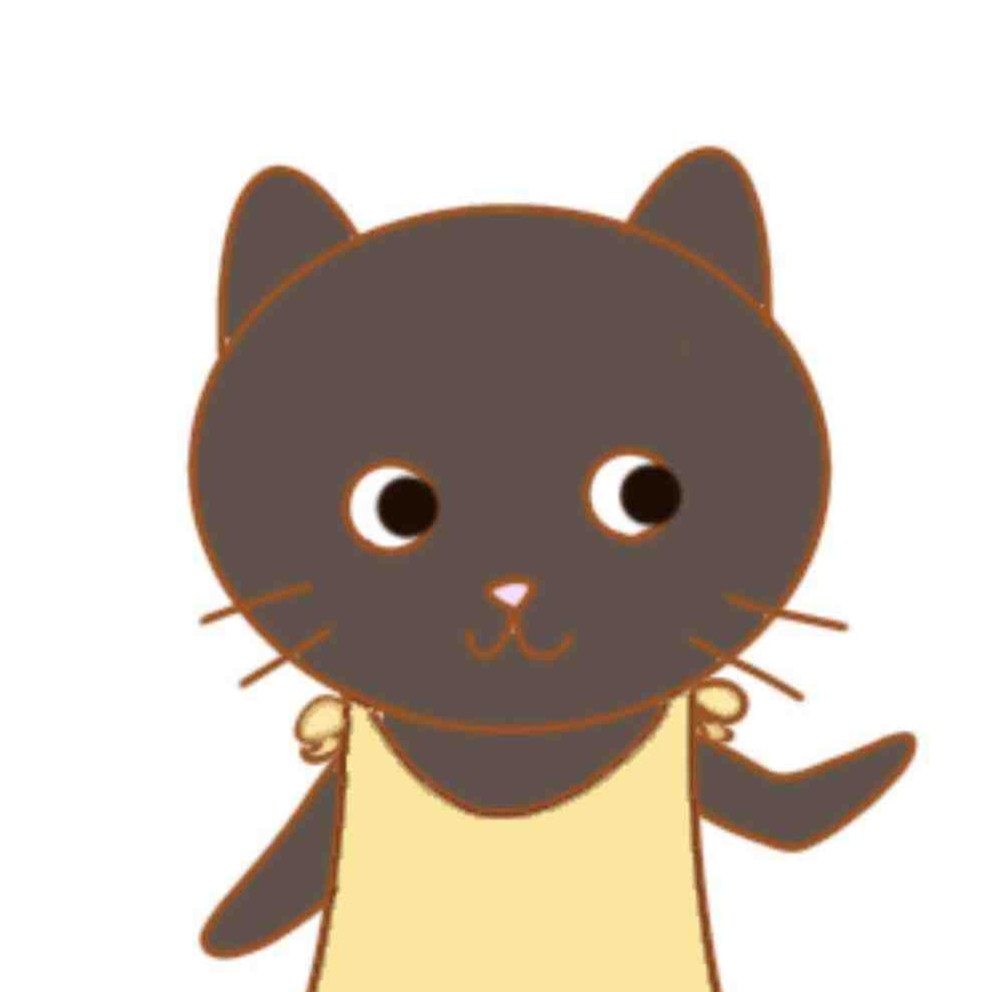
漢方薬でも副作用が起きることがあるし、即効性があるものもあります。
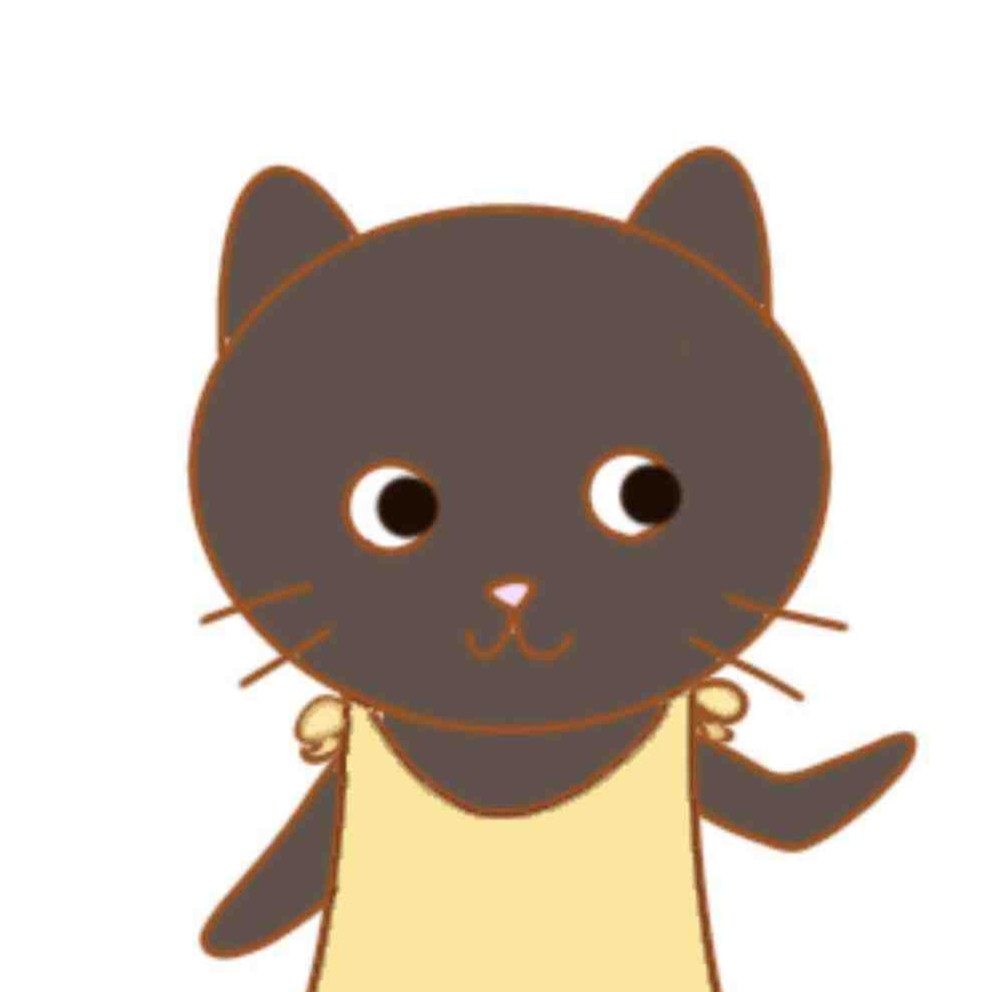
漢方薬の中には、ドーピング検査で陽性反応が出る可能性もあるんです。
ということで、ちょこっと漢方薬のお話を。
漢方薬とは
漢方薬とは、自然由来の生薬(しょうやく)を組み合わせて作られた医薬品のことです。
体質を根本から整え、病気の予防や慢性的な不調の改善に用いられます。
冷え性・ストレス・肌トラブル・アレルギーなど、原因がはっきりしない不調にも対応できるのが特徴です。
漢方薬とドーピング検査
漢方薬は「自然由来だから安全」と思われがちですが、使用される生薬の中には、国際的なドーピング規制(WADA基準)で禁止されている成分を含んでいるものもあります。
たとえば風邪薬としても有名な「葛根湯」や「麻黄湯」には麻黄が含まれています。
これらを飲んだ後にドーピング検査を受けた場合、麻黄に含まれるエフェドリンに反応する可能性があります。
禁止物質を含んでいなくても、漢方薬はすべての成分があきらかになっているわけではありません。
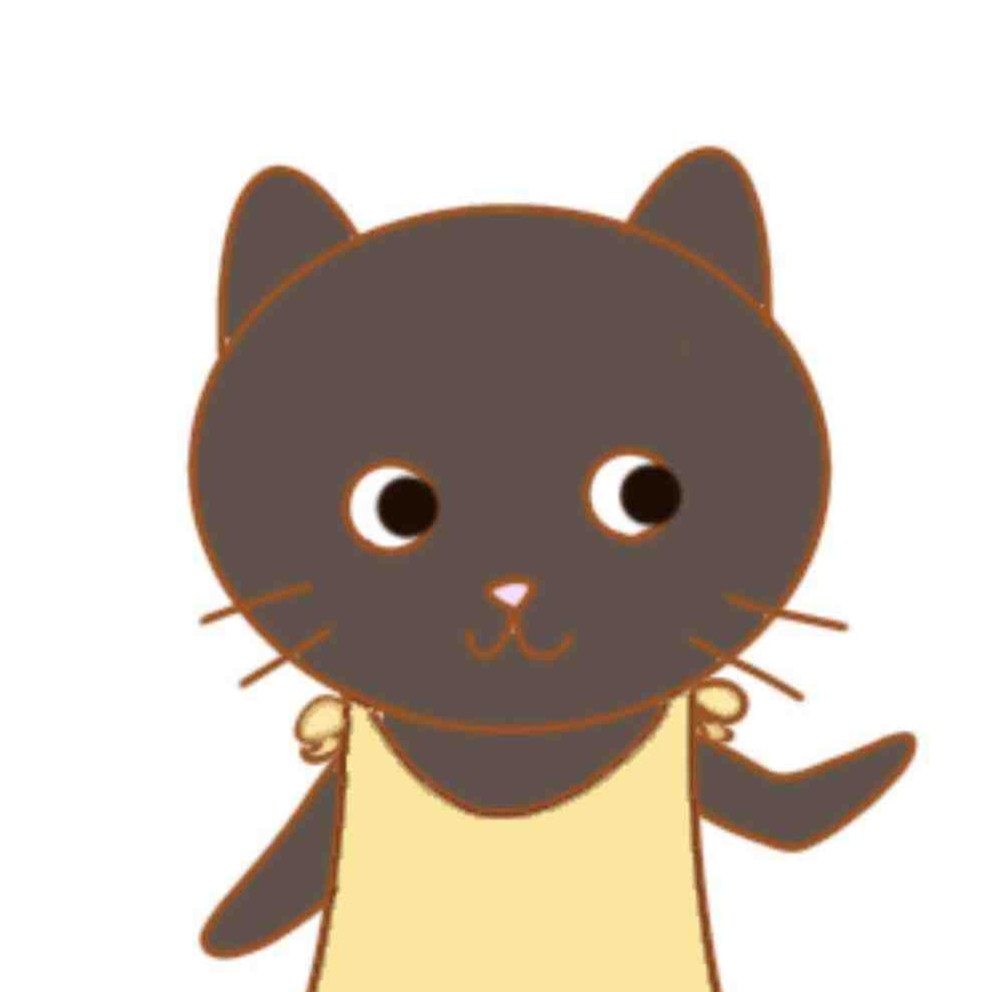
特に競技スポーツに関わる方は、自己判断での服用に注意が必要です。
漢方薬の主な種類
漢方薬には、形状や製造方法の違いによって、以下のような種類があります。
- エキス剤:生薬を煎じた液を粉末・顆粒状にしたもの。手軽で持ち運びやすいため、現在主流。
- 煎じ薬:生薬を自宅で煮出して飲む伝統的なタイプ。手間はかかるが本格的。
- 散剤:生薬そのものを粉末にしたもの。飲みにくさがあるが効果が強いことも。
- 丸剤:散剤を丸く固めたもので、比較的飲みやすい。
漢方薬の即効性
漢方薬はゆっくり聞くイメージがありますが、実は即効性のある漢方薬もたくさんあります。
特に急性の症状や、発症初期の段階で効果を発揮するものが多く、西洋薬と同じように頓服(症状が出たときに飲む)で使われることもあります。
漢方薬にも副作用はある?
「漢方薬は自然のものだから安心」と思われがちですが、副作用がないわけではありません。
体質に合わなかったり、生薬の特性により副作用が出ることもあります。
不調を感じるときは必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
副作用を避ける漢方薬の選び方
- 体質に合った漢方薬を選ぶ(自己判断しない)
- 信頼できる漢方専門医や薬剤師に相談する
- 市販薬の場合は、パッケージの効能・注意書きをよく読む
- 副作用が出た場合はすぐに服用を中止し、医療機関を受診する
漢方薬の正しい飲み方
漢方薬は水または白湯で飲むのが基本です。
苦みや匂いが苦手な方には以下の工夫がおすすめです。
- 口に先に水を含んでから薬を入れる
- オブラートで包んで飲む(ゼリー状にすると飲みやすい)
- 服用ゼリーに混ぜる
- お湯に溶かして飲む(味が強く出て、飲みにくくなる場合もあるので注意)
- 錠剤タイプを選ぶ
オブラートや服用ゼリーの用意が難しいときは、アイスクリーム(特にチョコアイス)、ココアなどでも代用できます。嫌な風味を、感じにくくしてくれますよ。
服用のタイミングと保存方法
服用は空腹時に
漢方薬は食前または食間の空腹時に飲むのが基本です。
「食間」というと「食事の合間に飲む」と勘違いされていることがありますが、これは「食中」。
「食間」とは、食後2〜3時間後の、食べ物が胃の中からなくなった頃ということです。
「食前」というと「食事の直前」と思い、薬を飲んですぐ食事をはじめる人もいますが、この飲み方は、「食直前」です。
正しい「食前」は、「食事の30分前」なんです。
ただし、食前や食間に飲み忘れてしまう場合は、医師に相談のうえ、食後の服用に変更できることもあります。
保存方法
-
- 直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管する
- エキス剤や煎じ薬は、湿気や温度変化に注意
- 開封後は早めに使い切る(特に煎じ薬や粉末)
旅行時の持ち運び
- 1回分ずつ小分けにしておくと便利
- 高温多湿を避け、ジッパー付きの袋などで密閉する
- 心配な場合は保冷バッグを利用する
まとめ|漢方薬を正しく使って、体の内側から整えよう
漢方薬は、体質や不調を根本から整える自然由来の医薬品です。
副作用が少ないイメージがありますが、体質に合わない成分や使い方によっては副作用が起きることもあります。
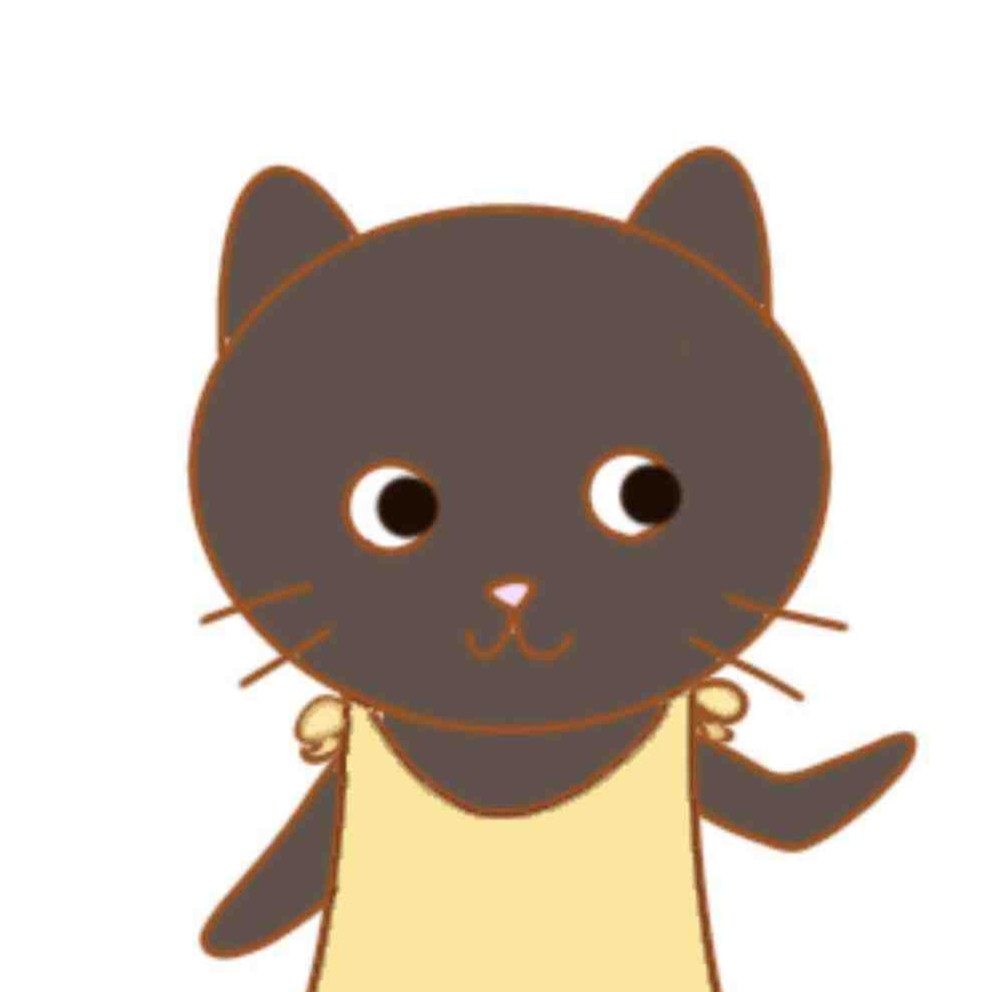
正しく選び、正しく飲むことで、漢方薬はあなたの健康に寄り添う頼れる存在になります。
飲み方の工夫や服用のタイミング、保存方法などを守りながら、自分のペースで続けてみてください。










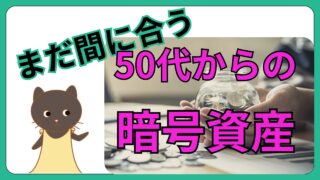



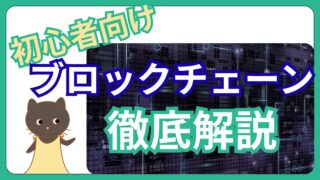






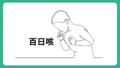

コメント